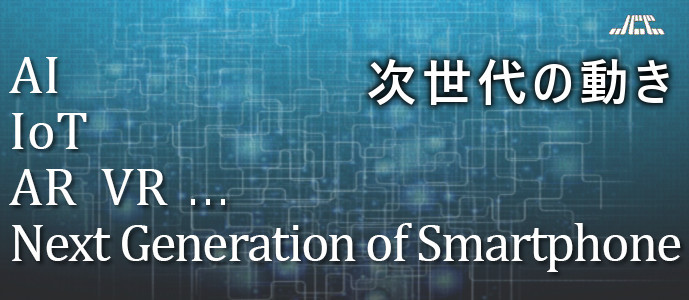スターリンク狙う中国の論文(7月3日)
スペースX社は米国フロリダ州のケネディ宇宙センターでファルコン9ロケットの打ち上げに成功し、スターリンクの通信衛星53機の打ち上げに成功した。スターリンクはウクライナ戦争でも活躍しており世界的に有名である。
こうした中、中国の科学ジャーナル雑誌「モダンディフェンステクノロジー」に掲載された論文がスペースX社のスターリンクについて、潜在的なリスクであり、これを監視し、場合によっては機能を停止させ、破壊する手段を確保しておく必要があるという論文を掲載した。...
全部読む
スペースX社は米国フロリダ州のケネディ宇宙センターでファルコン9ロケットの打ち上げに成功し、スターリンクの通信衛星53機の打ち上げに成功した。スターリンクはウクライナ戦争でも活躍しており世界的に有名である。
こうした中、中国の科学ジャーナル雑誌「モダンディフェンステクノロジー」に掲載された論文がスペースX社のスターリンクについて、潜在的なリスクであり、これを監視し、場合によっては機能を停止させ、破壊する手段を確保しておく必要があるという論文を掲載した。
スターリンクを撃ち落とすことはそう簡単ではなく、物理的な破壊攻撃に対してある程度の強度を確保しているだけでなく、2000基以上の衛星群を連携させている為、仮に1基が稼働不能に陥ったとしても、その影響は小さい。
もうひとつ、スペースX社のイーロンマスクCEOが中国との敵対関係にないということもある。マスクは中国・清華大学経済管理学院の諮問委員長であり、習近平国家主席とも個人的に親しい。
さらに人権問題で国際社会の厳しい目線が注がれる中、新疆ウイグルにテスラ社のショールームまで開設し、実は中国人にマスクは人気すらある。
マスクのような人物が民主国家と専制国家の間で不測の事態が生じた際、パイプ役になることを期待したい。
閉じる
メタバースで進化する半導体(7月2日)
メタバースは「超えた」という意味を持つメタと、「宇宙」を意味するユニバースを掛け合わせた造語である。
基本構造としては、ネットにつないだ仮想3D空間の中で、参加者が自らのアバターを作り、他の参加者とコミュニケーションし、商品を売買しながら、お金・人・もの・文化などを共有しつつ、現実世界とは別の「想像世界」を現実世界と同じように作り上げていくものである。
メタバースを行うためにはSNSのような既存のネットよりもさらに複雑化した技術、より高速で高性能なデータ処理、膨大なデータを転送・蓄積できるネットワーク環境、および表示能力が向上したAR/VR機器装置などが必要とされる。...
全部読む
メタバースは「超えた」という意味を持つメタと、「宇宙」を意味するユニバースを掛け合わせた造語である。
基本構造としては、ネットにつないだ仮想3D空間の中で、参加者が自らのアバターを作り、他の参加者とコミュニケーションし、商品を売買しながら、お金・人・もの・文化などを共有しつつ、現実世界とは別の「想像世界」を現実世界と同じように作り上げていくものである。
メタバースを行うためにはSNSのような既存のネットよりもさらに複雑化した技術、より高速で高性能なデータ処理、膨大なデータを転送・蓄積できるネットワーク環境、および表示能力が向上したAR/VR機器装置などが必要とされる。
メタバースの普及にともなって、半導体産業も本格的に動きだしている。メタバースには演算をより速く大量にこなせる高い処理能力がある先端半導体(高速大容量半導体メモリー、HPC(高性能演算)チップが求められている。
これによって先端産業全体が底上げされ、巨大データセンター、5G通信などの開発も推進されるなどの産業的展開が期待されている。
米国・インテルはメタバースについての声明を発表し「真のメタバースの実現には現在の1000倍のコンピューティング能力が必要になる」と述べ、今後インテルとしてはメタバース分野への対応を強化していくとしている。
インテルは21年6月にGPUを担う事業部門を立ち上げAMDから幹部を迎え入れるほどの力の入れようである。
メタバースへの投資熱が世界で高まっていけば、半導体の進化が一気に進みそうな気配をみせている。
閉じる
半導体に巨額投資進める台湾の真意は?(6月25日)
台湾は10ナノ未満の最先端半導体製造において世界シェア92%を占めている(8%は韓国)。台湾は現在、空前の半導体投資ラッシュである。
その投資額は驚くべきことに約16兆円で、日本の国家予算のおよそ6分の1である。その資金で何をしているのかと言えば、TSMCを含めた4企業(UMC、南亜科技、力晶)による20の新工場を建設中である。
北は新北から、新竹、苗栗、南は台南、最南部の高雄まで台湾全土に及んでいる。...
全部読む
台湾は10ナノ未満の最先端半導体製造において世界シェア92%を占めている(8%は韓国)。台湾は現在、空前の半導体投資ラッシュである。
その投資額は驚くべきことに約16兆円で、日本の国家予算のおよそ6分の1である。その資金で何をしているのかと言えば、TSMCを含めた4企業(UMC、南亜科技、力晶)による20の新工場を建設中である。
北は新北から、新竹、苗栗、南は台南、最南部の高雄まで台湾全土に及んでいる。これらの敷地面積を合わせると東京ドーム40個分以上になる。台湾がこれほどまでに半導体に力を注ぐ理由を、国立台湾大学「重点科技研究学院」のケツシタツ院長に聞いてみた。
ケツシタツ院長は「台湾には石油のような資源がない。その一方で、半導体が戦略的な資源となっていて、例えば中国が台湾に侵攻すれば、半導体のサプライチェーンが破壊され、工場が止まってしまうことになり、世界はそれを許さない。再稼働するまでに少なくとも半年から1年間止まってしまい、その間世界経済全体がストップしてしまうからだ」と述べた。
台湾にとって最大の対中防御策は、もはや米国から供与される武器などではなく、自前で揃えた最先端の半導体工場なのかも知れない。こうした台湾の手法は資源がない日本にとっても大いに参考となるものである。
つまり、「世界にとって不可欠な存在になる」ことで自分たちを守るという発想である。日本も世界に真似できない半導体装置や部材で自国を守るという発想を持つべきである。他方、中国はそれでも台湾に戦争を仕掛けて、半導体物資を台湾まるごと取ってしまおうとするかもしれないという見方もある。こうした事について、米国政府の非公式の代表団として台湾を訪問している米国のアーミテージ元国務副長官が、3つの理由をあげ、否定した。1つ目はウクライナにおけるロシア軍の多大な犠牲を中国が見ていること。2つ目は新型コロナによる都市封鎖で中国国内の経済活動が低下していること。3つ目は台湾への攻撃が地理的に非常に難しいことである。
台湾の安全保障は、ほぼ「半導体」の一本足打法に頼り切っているが、狡猾な中国は必ずどこかに隙を見つけて突き崩しにかかる可能性もある。いざとなったらいつでも米国や日本に移転できるオプションを同時に考えておく必要もあるだろう。
閉じる
バイデン政権が注目している半導体戦略(6月18日)
経産省はTSMCとソニーグループ、デンソーが熊本県に作る先端半導体工場の整備計画を認可した。最大で4760億円を交付する。新工場は2024年操業予定で、27ナノ以下のロジック半導体が作られる予定である。
デジタル化・電動化が進む中、産業のコメと呼ばれる半導体は戦略物資であり、スマートフォンから戦闘機まで用途が幅広く、国際競争力を左右する経済安全保障の上でも重要な物資である。そのため日本や米国、中国、欧州など各国が巨額の補助金を出すなどしてTSMCやサムスンなど、有力半導体会社の誘致に動いている。...
全部読む
経産省はTSMCとソニーグループ、デンソーが熊本県に作る先端半導体工場の整備計画を認可した。最大で4760億円を交付する。新工場は2024年操業予定で、27ナノ以下のロジック半導体が作られる予定である。
デジタル化・電動化が進む中、産業のコメと呼ばれる半導体は戦略物資であり、スマートフォンから戦闘機まで用途が幅広く、国際競争力を左右する経済安全保障の上でも重要な物資である。そのため日本や米国、中国、欧州など各国が巨額の補助金を出すなどしてTSMCやサムスンなど、有力半導体会社の誘致に動いている。
日本ではTSMCばかりが注目されがちであるが、実は米国の半導体会社インテルも2023年に日本に上陸する。インテルが54億ドルで買収したイスラエルの半導体会社・タワーパートナーズセミコンダクター社のサプライチェーンが富山県魚津市の工場でレガシーチップの生産を担う予定である。
こうした動きの背景にいるのは米国・バイデン政権である。バイデン政権としては純米国企業であるインテルに育ってもらいたいと考え実はインテルに力を入れている。
台湾海峡の地政学的リスクが強まる中、米国は半導体生産が集中する日韓や台湾と共にChip4(半導体同盟)の結成を目指し、ハイテク技術で覇権を争う中国に対抗していく構えである。
日本としては製造装置とか部材の強みを生かし、米国と共に次世代半導体開発を一緒にやっていくという強い意思がある。特に量子コンピューターや人工知能でのユースケースを広げていくビジョンを持って先に進んでいくというポジティブなスタンスは重要である。
閉じる
最先端半導体を巡る台湾の動き(6月11日)
台湾の地政学リスクが何度もささやかれる中、台湾では総額16兆円規模の未曽有の半導体の投資ラッシュが起きている。台湾「TSMC」など4企業が台湾全土に20の新工場を建設中か、完成させたばかりである。
台湾が半導体の巨額投資に突き進んでいる背景には半導体大国として独自の存在感を示したいという思惑があるとみられる。TSMC・マークリュウ会長はかつて、米中両国を念頭に「将来的に情報交換が不自由になり、太平洋の両側で自国の供給網を自己完結化させる動きが出ている」とした上で、「開発と製造にかかる費用が増大する」などと懸念を示したことからもわかるように、米中の政治的な動きにからめとられたくないというのが台湾=TSMCの本音のところである。...
全部読む
台湾の地政学リスクが何度もささやかれる中、台湾では総額16兆円規模の未曽有の半導体の投資ラッシュが起きている。台湾「TSMC」など4企業が台湾全土に20の新工場を建設中か、完成させたばかりである。
台湾が半導体の巨額投資に突き進んでいる背景には半導体大国として独自の存在感を示したいという思惑があるとみられる。TSMC・マークリュウ会長はかつて、米中両国を念頭に「将来的に情報交換が不自由になり、太平洋の両側で自国の供給網を自己完結化させる動きが出ている」とした上で、「開発と製造にかかる費用が増大する」などと懸念を示したことからもわかるように、米中の政治的な動きにからめとられたくないというのが台湾=TSMCの本音のところである。
もうひとつ、台湾が最先端の半導体大国になることで、有事の際にもウクライナのように扱われないようにするという布石を台湾・蔡英文総統は打っているのかもしれない。例えばウクライナに核兵器があれば、ロシアの侵攻を招かなかったと言われているが、蔡英文総統は核兵器に代わるカードとして半導体を考えているのではないかという仮説も成り立つ。
一方、米国としては最先端の半導体工場をリスクが高い台湾から米国本土に移転させたいと思っているが、今回の台湾の動きはその思惑に逆らっているようにも見える。
米国の強みはアーキテクチャー系の半導体会社が多いことであり、台湾が最先端半導体に強くても、現段階では米国抜きでは立ち行かないことは確かである。
懸念されるのは中国の動きである。台湾への武力侵攻も当然危惧されるが、政治的に台湾統一を叫ぶ中国は本音のところでは台湾の半導体産業を手中に入れたいと考えている。
TSMCの上層部を完全に親中国に変えてしまう工作や、例えばロシアがウクライナの穀物の輸出入を妨害して世界に打撃を与えているように、中国が台湾からの半導体の輸出入を妨害するなど嫌がらせをして圧力をかけてくることも考えられる。その時、日本や米国、世界の産業界はどう動くのかといった様々なケースをシミュレーションしておくべき時を迎えている。
閉じる
「世界の新技術」内の検索